予防しようがない!?今や8人に1人の国民病と食品表示問題
今や日本国民の8人に1人が罹患していると推計されている国民病、慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease; CKD)。その最大のリスク要因として、食品添加物として使用されている無機リン化合物の習慣的多量摂取が指摘されており、食品関連業界の非協力的姿勢で深刻な社会問題となっています。FMGは、現時点でデパ地下やスーパーの惣菜コーナーで販売されている加工食品(惣菜)の大部分に、何らかの目的でリン酸塩が添加されていることを問題視しています。それは、「デパ地下やスーパーで惣菜を買う習慣を止めないかぎり、いつ慢性腎臓病(の兆候)を指摘されてもおかしくない」といっても過言ではないほどです。とくに、デパ地下の対面販売では、惣菜の原材料情報すら表示されていないことも多く、店頭で情報開示を求めても何分も待たされる有様。食品添加物問題に関して、よほどの自衛意識がないかぎり、知らないうちに無機リン添加食品をつかまされていることになっているわけです。
そこでFMGでは、多くの内科医が共通して指摘する慢性腎臓病の原因、無機リンの問題に徹底的に焦点をあて、化学専門家目線でレビューすることにしました。
無機リンとは?それらの理化学的特性と健康影響との関係について
食品添加物として使用される無機リン化合物として考えられる物質としては、以下のようなものが挙げられます。
- リン酸(一リン酸)
- リン酸二水素塩(酸性リン酸塩)
- リン酸一水素塩(中性リン酸塩)
- リン酸塩(塩基性リン酸塩)
- ピロリン酸塩(二リン酸塩)
- ポリリン酸塩(三リン酸塩)
リン酸はコーラなどの低廉な酸味料として使用され、リン酸二水素塩も酸性のため、酸性域でのpH安定化(pH調整剤、酸味料、ソルビン酸等の保存料の抗菌性発現)や、カルシウム塩がベーキングパウダー(合成膨張剤)の酸剤として使用されたりします。リン酸水素塩はpH7前後の中性域でのpH安定化(pH低下による変質防止)やタンパク質(とくに動物性)の改質・結着(接着)・柔軟化・水分保持、チーズや油脂乳化クリーム(乳クリーム・植物性ホイップ)の乳化安定の目的で使われています。インスタントラーメンやインスタントうどんのスープにも使用されています。リン酸塩(塩基性)は、ラーメンなどのかんすいの成分として、他の塩基性化合物(炭酸カリウムなど)とともに使われたりします。
ピロリン酸塩は、リン酸が2分子縮合したかたちのピロリン酸の塩であり、一リン酸塩と同様の使われ方をされることが多いですが、とくに、冷凍フライドポテトの保水・変色防止や、クリームの乳化安定に使用されていることが多いようです。ピロとは、「炎」「高温」を意味する接頭辞で、リン酸を強熱して得られることから、その名があります。
ポリリン酸塩は、正式にはトリポリリン酸塩といい、リン酸が3分子縮合したかたちをとっているトリポリリン酸の塩です。その分子構造から、タンパク質の物性に大きく影響を及ぼす金属イオンを捕捉する能力が大きく、とく金属イオンの作用をマスキングすることによる畜肉類の軟化や結着に使用されることが多いようです。かつては、有リン洗剤のビルダーとして使用されて、水質汚濁で問題になったこともあった物質です。
以上のことからお気づきのように、三価の弱酸であるリン酸の塩は、食品で有用な弱酸性域(リン酸二水素塩)または中性域(リン酸一水素塩)のpHで安定化させる特性が優れており、加えて、急性中毒のリスクが非常に少なく、これが不調の原因になることが非常に少なく、安価であるため、食品業界では好んで使われるのです。
一方で、リン酸やその塩には、中性付近、ないしはそれ以上のpH領域においては、金属イオンとの相互作用で不溶性物質を生成しやすいという理化学的特性があります。この理化学的特性は、リン酸結石の形成や血管内壁の硬化による内臓障害に関係しているのではないかと考えられるようになってきています。また、無機リンは有機リンと比べて吸収率が高く、少量摂取しただけでも過剰摂取になりやすく、意識的な制限が重要とされています。とくに、野菜や海藻のような吸収拮抗要素を多く含む食品の摂取が少なく、加工食品に過度に依存した偏った食生活の場合、無機リン過剰摂取の害をとくに強く受ける可能性が高く、注意が必要です。
食品成分としての有機リンは、レシチンや細胞膜を構成するリン脂質のかたちで含まれており、とくに動物性食品にはもともと有機リンが多いとされています。また、玄米のヌカ層に含まれているフィチン酸(イノシトール六リン酸)も食品由来有機リンです。有機態のリンは吸収率が低く、無機リンが添加されていない食品の場合、よほど食べ過ぎたりしないかぎり、とくに心配する必要はありません。
とれない疲れ、夏バテ、貧血の諸症状、尿の異常…腎臓の異常かも?
ドリンク剤でもビタミン剤でもとれない疲れや夏バテ、立ちくらみや運動時のしんどさといった貧血の諸症状、尿の異常、すべてそうだと断定はできませんが、他にとくに自覚する異変がないのであれば、これらの症状は、慢性腎臓病の予兆かもしれません。とくに、慢性疲労は、糖尿病とも密接に関係している可能性もあります。なぜなら、慢性腎臓病には、糖尿病性腎症のケースもあるように、糖尿病(とくに生活習慣が関係する2型)とも密接に関係しているからです。また、腎臓は肝臓や大腸とも密接な関係があるとされていて、肝臓や大腸の健康状態が改善することに伴って、腎機能の悪化が抑えられることもわかっています。腎臓が弱ると貧血になりやすいというのは、腎臓が赤血球の形成に欠かせない造血ホルモンであるエリスロポエチンを産生する主要な臓器であるためで、腎機能の低下により、そのエリスロポエチンの産生能力が低下することで、赤血球が減少し、貧血の症状が出やすくなるためです。
従来からよくいわれてきたように、腎臓は老廃物を尿として排出するフィルター様の役割が主要な役割としてありますが、そのフィルター様機能が低下すると、当然、血液には老廃物が残ったまま全身を循環することになり、その老廃物が蓄積されやすくなります。この異変が、解消しない慢性疲労や慢性炎症の原因になることがあります。このことは、クレアチニンや尿素(窒素)の異常に現れることがあるので、これらの物質は、腎機能の指標のひとつとなっています。
腎臓は毛細血管の集合体といわれますが、無機リン化合物の過剰摂取が常態化していると、先ほど示したような無機リン化合物の理化学的性質に起因して、血管内壁に不要物が固着し、腎臓の血管の硬化の原因になることがあります。このことは、腎機能の低下に直結する危険な現象であるために、加工食品への過度依存による無機リンの過剰摂取にはとくに注意するようにとの啓発がなされているわけです。
腎臓は沈黙の臓器といわれるように、腎臓そのものが「痛い」などの自覚症状を発することはほとんどないため、以前はあまり重要視されない時代があったことは否めません。しかし、それは遠い過去の話。近年では、腎臓は地味ながらも全身の絶対になくてはならない調整役として、むしろ「全身の中で最も大切にすべき臓器」という認識が、予防医学では常識となってきています。
透析送迎車を多く見かける隠れ要因?隠れリン酸塩「pH調整剤」の闇
最近、都市部の住宅地で、よく透析クリニックの送迎車をよく見かけませんか。それほどに透析が必要な重度腎臓病患者が多いことの証です。いろいろな背景が指摘されていますが、もし、「まさか、大丈夫だろう」と見逃していたあの添加物が原因のひとつだとしたら、どうでしょうか。今日の食品業界事情から考えれば、その可能性は高くても何らおかしくはないと、FMGは指摘します。なぜなら、医師の多くが摂取を意識的に控えるべきだと注意喚起する食品添加物の無機リンが「pH調整剤」という合法的隠蔽表示によって、無意識のうちに摂取させられている機会が多いからです。あなたは、これまで「pH調整剤」の表示が、リン酸塩を含む可能性を示していることをご存知だったでしょうか。pH調整剤として考えられる他の物質としては、クエン酸塩やフマル酸塩などの多価有機酸塩などが考えられますが、成分の内訳が表示されていなければ、化学的には、「含有の可能性を疑う」以上のことはできません。もし、pH調整剤を「クロ」ではなく「シロ」と判断しているのであれば、その判断は、今すぐ180度覆す必要があります。とくに、動物性食品(シーフードミックス、鮭などの切り身、魚肉加工品、加工肉(ハム、ソーセージ、サラミ、成形肉、タレ漬け肉など))やクリーム類にpH調整剤の表示がある場合は、リン酸塩含有の可能性が高いですので、迷わず避けるべきです。どうしても買いたい場合は、店員にpH調整剤の物質内訳を問い合わせし、リン酸塩を含むことがわかったり、そもそも回答ができない場合には、残念ですがその購入を避けてください。
このような「pH調整剤」の物質内訳の表示なき包括表示は、慢性腎臓病の予防行動の足かせになっている事態を重く受け止めたうえで、FMGでは、消費者庁と報道局の地域を所管する保健所に対して、pH調整剤のような包括表示だけの表示を認めない、物質内訳表示の義務化をいち早く実現するよう政策提言しています。
現在のところ、重度腎臓病に起因する透析治療は根本的な治療ではなく、延命治療とされており、一度始まると、一生、必須ルーティンとして、週に数回、1回あたり数時間、医療的に拘束されることになるとされています。透析になる前に予防するしか、透析を回避する方法はありません。腎臓は肝臓などとは異なり、再生力がきわめて低い臓器のひとつとされており、一度低下した腎機能の改善はきわめて難しいと考えられています。だからこそ、わずかな異変にもいち早く気づき、日頃の食生活や生活習慣(運動・睡眠など)を見直し、小さな改善を積み重ねていく予防行動が何より重要となります。もし、気になる兆候があるようであれば、お近くの腎臓内科の専門医に相談してください。
医師や薬剤師、管理栄養士発の情報も、化学専門家の情報にも、それぞれ信頼できることもあれば、信頼できないこともあるかもしれません。FMGでは、化学専門家として、信頼できる化学的考え方を、他分野の専門家の情報のレビューとの整合性を保ちながら提供できるよう、努めてまいります。記事の信頼性には万全を期しておりますが、FMGの愛読者のみなさまも、クロスチェックとして、他の情報源もあわせてお読みいただくことを強くお勧めします。


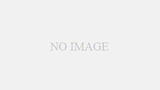
コメント