

ポケカ問題の本質は教育問題
ポケットモンスター(通称(一般的商標):ポケモン;以下、ポケモン)とは、ポケモン(東京都港区;以下、ポケモン社)・任天堂(京都市)・ゲームフリーク(東京都千代田区)がその独占的権利を持つとともに、任天堂のゲームコンテンツで使用されている、非実在生命体キャラクター群と、それらによって展開されるフィクション・ストーリーシリーズを指します(権利表示を参照)。つまり、ポケモンは、自然界には存在しない、でっち上げられたキャラクターやそれらの特性を興味の対象とし、あくまでも現実の自然とは隔絶された仮想現実のポケモン世界の中に没入させ、囲い込むことで、相対的に外界となる現実世界への関心をもつ物理的機会及び精神的機会を奪わしめるロックイン(lock-in)型の収益モデルをとっているということになります。このような前兆は、今から42年前に、任天堂からファミリーコンピュータが発売されたことがきっかけで起こったファミコンブームの時代からみられ、当時としても大きな教育問題になりましたが、ことに近年のポケモンブームは、それだけで会社ができるまでに過熱し、その仮想現実世界への没入の程度も、こどもや一部の成人の生活や価値観をも変えてしまうほどにもなり、単なる娯楽の域を超えた、より深刻なものとなっています。
FMGと銀鮒の里学校は、このポケモンカードなど、ポケモンをめぐる一連の問題の本質(根底)は、教育問題であり、これまでの教育施策の失策の集大成であるとして、教育問題としての、各主体の自覚を促すべく、独自の啓発を行っています。とくに、動植物の精緻な観察や、それに基づく論理的考察を習慣化するといった自然軽視の教育は、商業的ゲームへの没入に対する無批判な今日の社会をもたらし、学校や家庭、社会が「儲かりさえすればよい」「低収入は悪」といった経済評価主義や拝金主義をこどもたちに刷り込むことによって、都会優位・農漁村劣位という潜在意識を植え付けてきたことで、究極的には、都市への人口流出と農漁村の過疎・限界集落化を一気に加速する人口問題や、農業の衰退を招いてきたのです。例えば、今日の親は、こどもに対して、「将来は商社マン(のような高収入)になってほしい」とか「農家(のような低収入)にはなるな」という願望をもち、そのような願望の実現こそが、親がこどもの教育に力を入れる目的になっているということをよく聞きませんか。そのような願望を持つかぎり、都会への人口流出と農漁村の過疎は必然だということに気づきませんか。各子育て世帯や社会の一人ひとりの意識という微分に、思考停止や同調的決め付けがあるのであり、それらの積分解として、今日の日本社会の人口問題として現れているということなのです。
行き過ぎた商業主義がもたらした「ポケカ証券」の社会病理
「数枚で定価200円足らずのポケカが10万円にも、100万円にも」
常識人であるかぎり、気が狂いそうな話ですが、これは現実です。テレビメディアなどの報道でも、このような気が狂いそうな社会現象に、違和感を訴えずにはいられないという旨の報道が相次いであります。スポンサーがつく営利メディアでもこの論調ですから、いかにおかしいかがおわかりいただけるかと思います。今や、「ポケカは収益性の高い有価証券」という認識が、とくに若年層の大人にはあるといいます。この世代は、10〜30年くらい前に義務教育を受けてきた世代にあたります。この頃は、ちょうどビデオゲームやカードゲームに対する低俗感や害悪感が和らぎ、これらに対する社会からの風当たりが緩んできた頃に重なります。さらに今日では、ポケモン社やeスポーツのように、非実在キャラクター群やゲーミングの機会自体が企業化・職業化するほどのエスカレートぶり。少なくとも、それより昔の昭和の頃に義務教育を受けてきた世代にとっては、これらの商業的娯楽は、教育への悪影響の懸念が強調されたこともあり、あり得ない社会的変化です。
別の言い方をすれば、ポケカは非現実の虚像をカードという形で仮想的現実化することに対して投資し、そのプレミアムによる見返り(リターン)を求めるという虚像投資といえます。今回のマクドナルドのハッピーセットのポケカ高額転売問題では、ポケカを有価証券として煽り立て、それがほしいという感情を高ぶらせている日本社会に目をつけた悪意ある転売者(転売ヤー)がメルカリや中国などの海外ネットオークションに出品し、複数個のセットで数万円から10万円以上、ひどいものでは、システム最高額の999万9,999円まで価格を釣り上げているということが実際に起きていることを、FMGでは確認しています。もちろん、これは、日本マクドナルドが、メルカリと連携して、転売ポケカの取り消しをメルカリに要請したと報じられたあとのことです。いかに対応が遅いか、互いに利益優先で、本気で対策するつもりが全くないことのあらわれだということも、このことからおわかりいただけることと思います。
ポケカ問題のアンチテーゼ具現化としての持続可能な農業の場
ふなあんが能勢町で教育農園の能勢・ぎんぶなのうえんを運営しているのは、このポケカ問題のアンチテーゼの具現化として、現実世界(栽培植物を含む農地生態系)を関心の対象とし、農産品を人の叡智と大地の恵みとして投資の対象とする実像投資の正しい価値観醸成の場とするためです。基本的に農業は、正直者の職業というように、努力が報われる仕事です。異常気象などのリスクはあるものの、作物は、作り手の正直な努力に対して正直に応えてくれる、それが、本来の農業というものです。しかし、今日のように、虚像への関心で歪められた社会の価値観の狭間で、「知らないものは関心がない」などという言い訳をされ、真面目に作っても見向きもしてくれないといった理不尽が現実になっているのです。知らないものをつくるというのは、ニッチで多様な選択肢を提供したり、他にはないオンリーワンに出会えることによってもたらされる現実世界観の拡大で、より豊かな社会の創出の機運を実感してほしいという思いがあるからこそです。有形無形問わず、現実世界でまだ知らない、現実にあるモノやコトを新たに知ることの喜びこそ、一人ひとりの人生を豊かにし、それが集まることで、社会全体を豊かにしていく原動力だと確信して、経済的利益度外視で活動しているのです。そのようなことを笑うことは簡単ですが、そこには、語らずとも、血のにじむような苦労もありますし、悔しい思いをさせられたこともありますし、ナチュラルリスクと向き合うことも余儀なくされ、ほんとうに命がけなのです。それでも愚痴や弱音を吐かない、誰でもできることではないのです。それでも続くのは、経済的価値をはるかに超える何かがあるから。その「何か」を各々で体験を通じて主体的に実感し、明日の、将来の夢を築くきっかけにしていただきたいのです。
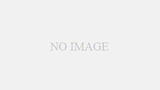

コメント