マクドナルドやヤマザキパン、コカ・コーラを禁止する納得の理由
「銀鮒の里って、なんて素敵な気づきを与えてくれるんだ!」「銀鮒の里の気づきがなければ、廃人一直線だったかと思うと、感激で大人泣きしてしまいそう!」
この記事を読んで、強く共感する人は、きっと有能な人だと思います。自信を持ってください。
一方で、FMGの記事を読んで、耳が痛く、「でも、私は…」と、できない言い訳をしては、逃げるように避けているような人は、近い将来、自業自得に猛烈に後悔することを覚悟すべきです。
キーワードは、「低AGEs」「低GI」「低リン」「低ナトリウム」の4低と、「高食物繊維」「高PCs(ファイトケミカル)」の2高です。これは、多くの内科医をはじめとする医師も推奨する、新しい健康セルフケアのマインドセットとなっていることです。もうお気づきのことと存じますが、以前からこどもの食育・便育で頻出しておなじみの「まごわやさしい」で実現できることや、こどもにも大人にも通用する健全な食習慣であることに気づくのではないでしょうか。また、同じく頻出している「マクドナルドの禁止」「ヤマザキパンの禁止」の明確な根拠を構成することもわかるのではないかと思います。
では、これらのキーワード4低2高について詳説していきます。どれも重要ですが、意識的に減らすべき4低のほうが優先されるべきであり、その前提のもとではじめて、2高が効いてくるということが大前提となることを意識してお読みください。
低AGEs
AGEs(=Advanced Glycation Endproducts;終末糖化産物)は、十分な量の脂質の存在下、熱の作用でタンパク質と糖質とが不可逆的に化合して生成するとされる不特定物質の総称で、医療関係者の間では、不可逆的に生成してどうしようもない厄介者であることから、よく「サビつき」に喩えられます。早い話が、高AGEs食は、機械なら致命的な故障につながるような「サビつき」を、体の中でわざとつくるような食生活だということです。高AGEs食の象徴的存在としてよく槍玉にあがるのは、想像に易し、あのマクドナルドのセット、ヤマザキパンなどの菓子パン・調理パン(とくに高温の油で揚げるパンやドーナツ菓子)、ポテトチップスなどのスナック菓子です。これらを禁止するだけでも、かなりのAGEsを削減できるほど、これらの食品は、AGEsの塊といえるほどのものです。その他、肉食中心となりがちな大部分の街の外食も、外食店として扱いやすいこともあり、唐揚げやフライなどの揚げ物が多く、高AGEs食になりがちです。その特性上、肉類や鶏卵、小麦グルテンなどといった高蛋白の食品を、多量の糖質(とくに砂糖やブドウ糖、小麦粉、ジャガイモ)とともに高温の油で加熱調理した料理や加工食品でAGEsの含有量が多くなりがちですので、可能なかぎり揚げ物を避け、揚げ料理から焼き料理や蒸し料理、煮込み料理に置き換えるなど、調理法を意識する必要があります。仕事柄、どうしても街中で外食をせざるを得ないことが多い人は、自身の健康を守るために、いつもの勤務先や出張先の近くの自然食・玄米食レストランや、野菜の煮付けや焼き魚などを選ぶことのできる昔ながらの食堂を見つけておくことをおすすめします。最近であれば、従業員の福利厚生の一環で、社員食堂で蒸し料理や煮込み料理などの低AGEs食に力を入れている企業もあったりしますので、確認しておきましょう。
低GI
GIとは、Glycemic Indexのこと、すなわち、摂取後の血糖値の上昇のさせやすさの指標となる値です。例えば、食後眠くなるという経験をされたことがあるのではないかと思いますが、そのような現象を「仕方がない」と放置してはいけません。その眠くなる原因こそが、血糖値の急上昇であり、そのような現象を繰り返していると、そう遠くないうちに、インスリン抵抗性を獲得し、糖尿病を発症するおそれがあります。糖尿病は免疫力低下による感染症リスクの増大や、腎臓疾患など多くの臓器の疾患とも密接に関係しているなど、さまざまな健康リスクを格段に高めることが問題視されています。
低GIと炭水化物の摂取を減らすこととは、必ずしもイコールではありません。同じ炭水化物摂取量でも、血糖値を上げにくい摂取方法があり、その違いを具体的に示す指標こそが、このGIという概念になります。例えば、同じ米であっても、白米のGI値は高く、最近では、それを理由にして、白米は日常的に食べるべきではないという医師も多いほどですが、玄米のGI値は低くなっています。玄米には、後述する健康上有益な抗酸化性物質などのPCs(ファイトケミカルズ)やビタミンB群も多く含んでいることもあり、毎日の主食を白米から玄米に転換することが推奨されています。玄米も正しく炊くと、とても美味しく食べることができますので、大人の健康管理だけではなく、こどもの食育としても、こどものころから玄米食に慣れさせるようにしましょう。やはり、精製糖質の塊(ハンバーガーやポテトなど)や流し込み(コーラ、シェイクなどのドリンク)ともいえるようなマクドナルドやヤマザキパンは、いうまでもないくらいに驚くべき高GI食であることにも気づくはずです。
低リン
高リン食は近年、とくに腎臓疾患や精神疾患などとの関わりで問題視されるようになっています。リンはとくに高タンパクの動物性食品に多く含まれていますが、とくに問題となっているのが、ただでさえリンが多い動物性食品の改質目的で多用される食品添加物のリン酸塩(無機リン)です。リン酸塩は、食肉の柔軟化、ミンチ肉加工品や成形肉、魚肉練り製品の結着(食品用接着剤)、乳化安定化促進(チーズ、ホイップクリームなど)、さらには弱酸性から中性域での緩衝能に優れていることから、pH調整剤としても多く使用されています。日頃から、スーパーやデパートの惣菜や弁当、冷凍食品や外食で動物性食品の加工食品を多く食べている人は、無意識のうちに高リン食になってしまっていることが多く、注意が必要です。これもやはり、マクドナルドやヤマザキパンでは、コカ・コーラの効果も借りて、いとも簡単に高リン状態となってしまい、危険ドラッグ並みに危険なリン酸スパイクを引き起こし、ポイ捨てやトラブルの原因となる乱暴行為など、社会的に問題の大きい行動に及ぶリスクも高いといえます。その手軽さや身近さも勘案すれば、数ある高リン食のなかでも、群を抜くほどの存在であることがわかります。
低ナトリウム
以前は、成人の食塩の一日摂取量は、10g未満、後に9g未満とされてきましたが、現在では、男性で7.5g未満、女性で6.5g未満(厚生労働省 日本人の食事摂取基準)と、さらなる低塩化が求められています。しかし、これでもまだ多すぎるという内科医師もいます。とくに、腎臓の健康状態が気がかりな人は、一日6g未満を目指すべきであり、食事療法の必要がない健康な人であっても、一日6g未満となるような食生活に慣れるべきだという意見もあります。実は、加工食品に頼らず、低糖質・低脂肪の、自炊(手料理)を基本とした健康的な食生活を送っていれば、一日6g未満はさほど難しいことではないのです。それが難しいと感じるのは、味の基準を、インスタントラーメンやマクドナルド、コンビニ弁当のようなものに置いているからです。実際に、これらの食品の食塩相当量を確認してみると、たった1食だけで、軽く4g以上を摂取してしまったり、ひどい場合は1食だけで6gを超過するような場合も少なくありませんから、難しく感じるはずです。(例えばラーメンでは1食だけで一発アウトです。)低ナトリウム食は続けてこそ意味があるわけですが、無理なく楽に、美味しいと感じなければ続きません。そのためには、やはり手料理で、酢やだし(ブロス)、食材本来の濃厚な風味で、食べたときの満足感を高める工夫をするのが、低ナトリウム食が続く秘訣となります。塩辛くなければ満足できないという不健康な思い込みはきっぱりと捨て、外食には極力行かず、惣菜なども極力買わず、納得のいく食事は自分でつくる(家庭の手料理で)という習慣を定着させることが、健康を守ることにつながります。
高食物繊維
食物繊維のなかでも、近年はとくに水溶性食物繊維の機能性が注目されています。もちろん、不溶性食物繊維も、それにしかできないような腸管内清掃効果や排便促進(うんこ量増加)の効果もあり、重要なのですが、水溶性食物繊維も意識的に同時に摂取することによって、不溶性食物繊維だけではカバーしきれなかったような腸管内清掃効果や排便量増加の効果があったり、前述のGI値低減に関与したりと、その重要性に注目する医師も増えているといいます。とくに、チコリや菊芋などのキク科野菜に多く含まれているイヌリンが、それ自体に糖質に似た柔らかい甘みがあることや、加えることで、食品の味がまろやかになることもあり、注目されています。イヌリンなどの水溶性食物繊維を多く含む食品を摂取した次の日に、ぜひ、親子でトイレで感激体験をされることをおすすめします。まずこども(小学生くらいを想定)がでっかいうんこを出したあと、ながさずに置いておきます。今度はこどもがしっかり温めた便座に座って、こどもと同じごはんを食べたおかあさんやおとうさんがうんこをしてみてください。大人うんこと差異がないほどのこどもうんこの大きさに驚かれると思いますし、おとなでも、これまでしばらくみたことのなかったような、小学生のようなすべすべで芳しい香りの極太うんこが出てスッキリする体験ができるはずです。ぜひ、親子同時にでっかいうんこを出してスッキリして、気づいてみれば、親子でほっかほかの手をつないで思わず笑顔になっていた…そんな快便体験を毎日実感するようにしてみてください。この快便体験からも、対極的なマクドナルドやヤマザキパンを食べたくなくなる強い動機づけになること間違いなしです。
高PCs(ファイトケミカルズ)
三大栄養素やビタミン、無機質といった主要栄養成分以外の植物由来の特有天然化学物質が、近年、健康面で注目されており、できるだけ多くの種類の植物性食品を食べるのがよいことの科学的根拠にもなっています。とくに、ポリフェノール構造を持つ物質やカロテノイドなどといった抗酸化性物質や、前述の玄米や米油に多いγ-オリザノール、玄米のぬか層に多いフェルラ酸が注目されています。ポリフェノールでは、アントシアニンを多く含むブルーベリーやケルセチンを多く含むタマネギなど、カロテノイドでは、人参やカボチャなど多くの緑黄色野菜に含まれるβ-カロテン、食用キンセンカの花などに含まれるルテイン、赤色トマトに含まれるリコピンなど、その他物質では、ブロッコリーなどのアブラナ科野菜に含まれている硫黄化合物スルフォラファンなどの摂取が推奨されています。当然ですが、PCsですから、植物性の食品を多く食べる習慣で自ずと摂取頻度は多くなりますから、とくにこれ、というよりも、日頃からできるだけ多品目の植物性食品の摂取を基本を据えた食生活を実践することが大切となります。もうおわかりのことと思いますが、やはり、マクドナルドやヤマザキパンではほぼ皆無です。
「疲れたら揚げ物・ビーフステーキ」はもう古い!「疲れたときこそ、あっさりとしたタンパク質と有機酸たっぷりの代謝賦活食」の新常識
これまでは、疲れたら唐揚げや豚カツ、ビーフステーキのような、こってりとした肉料理をガッツリ食べるのが効果的だと信じられてきましたが、これはもはや非常識になりつつあります。このような、一見して「元気が出そうな食事」は、AGEsやコレステロール、リンが多くなりがちで、血管を狭め、逆に身体に負担をかけて、寝ても疲れがとれにくいといった慢性疲労体質にする可能性が指摘されるようにもなりました。筋肉量の割に体重も重くなりがちで、運動の効率も悪くなって疲れやすくなるということも重なります。
そこで今、見直されているのが、前述の4低2高にかなう、生化学理論に基づいた、タンパク質量の割に、糖質や脂質が少なめで、加熱調理も強く行われておらず、解糖系に関係する有機酸をふんだんに活かし、爽快感や塩味増幅による満足感を高めた代謝賦活食です。具体例としては、カツオのたたきやもずく酢、粗製海塩で軽く塩味をつけたスチーム野菜(じゃがいも・人参・カボチャ・ブロッコリーなど)、納豆、大麦入り玄米ご飯などがあります。これらは、油で揚げる調理過程がなく、生または蒸しや軽い炙り程度の、さほど強度の強くない加熱調理にとどめられています。もちろん、生食で衛生上のリスクがあるような食材は十分な加熱を行う必要はありますが、そのような場合でも、揚げるなどの強い加熱は必要なく、中心部まで一定以上の温度で一定以上の時間を経る工程を経ていれば十分です。揚げ物や焼き料理も全く食べてはいけないわけではなく、できるだけ減らすように、日々意識することが大切です。記者も現在、ほぼ毎日のように、自転車で豊中から能勢まで農作業で走っていますが、4低2高の食事マインドセットを見直し実践して、体重や腹囲の健康的な減少と、運動効率の向上による疲労感の軽減・疲労質の前向きな変化を実感できています。年齢を重ねて、食事だけではメンテナンスしきれないような場合には、補助的にビタミン剤を服用するのもよいと思います。誰しも、与えられた時間も身体能力も限られています。そんな有限性を意識しつつ、ジャンクフードは悪い誘惑しかないという揺るぎない考えを持ち、4低2高マインドセットで食生活の質を高めて、仕事のパフォーマンスの最大化を図り、濃密で充実した人生を楽しみましょう。
※ この場合の「多くの専門家」とは、内科医師、管理栄養士、看護師など、食生活・栄養指導に関係する諸分野を専門分野とする専門家のことです。この記事は、これらの専門家が発信する情報のなかから、とくに多くの支持が得られている情報を厳選し、化学や科学リテラシー(ファクトチェック)の専門家であるFMGの記者、オカヤマンヘンな鮒がFMGに最適化レビューした記事です。安心してご利用ください。なお、この記事の内容と共通する推奨事項は、内科医師等の専門家が配信するYouTubeやウェブサイト、専門家監修の他のメディア記事でも確認することができますので、ぜひ、あわせてご確認ください。かかりつけの医院等で個別の医療的指導を受けている場合は、必ずその医師と相談のうえでご利用ください。


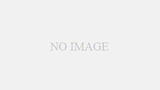
コメント